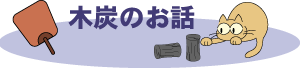 -
木炭は薪とはちがう!
- ホームセンターに行くと6kg390円の輸入木炭がドッカ〜ンと山積み。
輸入木炭のあまりの安さで感覚がおかしくなったのか?
木炭と薪の違いがわからずか?
キャンプ場へ行くと木炭を薪のようにどっと燃やしている人を
たくさん見かけます。
安いのはおおいにけっこうなんですが、
価格にかかわらず大切に使ってほしいですね。
森林保護なんておかまいなしで伐採した木材ですから・・・・・。
-
- でも木炭のことがわかっていればこんな使い方はできないはずなんです。
子供の炭焼き体験がはやっているそうですが、あれって意味あるのかも。
あたりまえの事なんですが単に何かを加熱するだけなら、
木をそのまま燃やす方がずっと効率的で安上がり。しかも環境負荷も少ないです。
木が炭になるまでには相当な熱エネルギーを発散してしまうので、
単に熱エネルギーとして考えるなら炭はものすごく効率の悪い燃料なんです。
暖炉やストーブに木炭をくべる人いませんよね。
安いからといってやたらと燃やすのはどうかと思いませんか?
|
「木炭」と「薪」の違いを再度確認してみましょう。
|
木炭の特性
- 1. 薪のような炎は立たない。
- 2. 煙がでない。
- 3. 火が消えず扱いやすい。
- 4. 燃焼時間が長い。
- 5. 火力が安定している。
- 6. 空気によって燃焼温度を調整できる。
- これは「炭焼き」という長時間の労力によって
生みだされた特性です。
価格にかかわらず木を炭にするには
相当な労力と熱エネルギーを使っていますので、
大切に使ってください。
|

木炭ができるまでには
すごい熱エネルギーを
消費しています。
これは紀州備長炭(白炭)の
窯出し。
|
木炭を作るには
- 木を燃やすと一時的には炭(熾き火:おきび)にはなるものの
短時間で燃え尽きて灰になってしまいますよね。
で、どうしたら木炭になるのかというと
「蒸し焼き」という状態にすると木炭になるんです。
蒸し焼きとはどういう状態かというと、
木炭の原木に線香が燃えるかのごとく火を着けて、
炎を立てず、ぎりぎり消えない程度に空気(酸素)を与えて
燃焼させる状態のことです。
この状態をうまく作り出すのが炭焼きさんの技術で、特に備長炭のそれは難しく、
その昔、紀州備長炭が紀州藩の大きな財源となっていた頃は、
藩の機密事項として外部に製造ノウハウが漏れないようにしていたほど。
現在でも一人前の炭焼きになるには10年ほどかかると言われるほど
高度な技術なんです。
もちろん炭質にこだわらなければ誰でも炭焼きができますので、
機会があれば是非ご体験を。
|
木炭の歴史
- 製炭された最古の炭は30万年も前のものが発見されているそうです。
ただ、一般に普及したのは近年で明治時代になってから。
それまでは一部の貴族などが使用していた贅沢品だったようです。
- 日本で最も多く木炭を使用したのは1940年(昭和15年)の約270万トン。
ほとんどが一般家庭で消費されていました。
七輪の生産量もこの頃がピークで、石川県の珠洲市では主要産業として
相当な数の天然岩切り出し七輪(この頃の七輪は切り出しが普通でした)が
製造されていました。
都心では夕食時ともなると各家庭の軒先から一斉に七輪の煙が立ち上ったとか。
戦後では1957年(昭和32年)の約222万トンが最大。
1995年の消費量は1957年のわずか1.4%程度。
100〜200分の1程度の消費で、しかも飲食店などの使用が多く、
家庭での使用はかなり少ないようです。
しかし、最近では特に炭焼き料理のお店が多くなり(ブームかな?)、
それにともないアウトドアはもちろん家庭での炭焼き料理も
増えてきたように思います。
炭火料理のおいしさを知ってしまったためでしょうか?
お年寄りはみんな知っていた!
グルメとしての贅沢な料理手法として、ますます増えてゆきそうです。
|
木炭の基礎知識
- 木炭には黒炭(くろずみ、こくたん)と、白炭(しろずみ、はくたん)の
2種類があります。
- 一般的に多く普及しているのは黒炭で、白炭は備長炭が有名です。
黒炭・白炭は製炭方法の違いで区別され、原木の種類による違いではありません。
どのような木でも黒炭・白炭のどちらにでも製炭できます。
- 黒炭は、蒸し焼きされた木炭の窯を密封して酸素の供給を絶ちきって消火し、
窯が冷えてから木炭を取り出したものです。
これとは逆に白炭は、蒸し焼きされた木炭の窯口を少しずつ空けて空気を送り込み
木炭を燃焼させます。窯から取り出す時は大きく口を開けて、
1200度ほどの高温で燃焼中の木炭を取り出し、
水分を含んだ土と灰の混ざった消し粉をかけて消火させます。
この粉が白く炭の表面に残るため白炭と言われます。
洗えば黒炭でしょうか?いえ黒くなっても白炭です。
実際には白ではなく灰色そのものです。
- 備長炭は全て白炭ですが、白炭は全てが備長炭ではありません。
樫以外の原木を白炭として焼いても備長炭とはいいません。
- どのような木でも黒炭・白炭のどちらにでも製炭できますが・・・
実際には商品価値がありませんから、
黒炭・白炭の原木はおおむね分類されています。
-
- 黒炭:クヌギ、ナラ、クリ、マツ、ブナ、シラカバ、ツバキ、竹など多数。
- 原木が不足していた戦時中などは、どんな原木でも黒炭にしたようです。
ただ、繊維質にしまりのない針葉樹は、木炭には不向きです。
国産の代表格はクヌギで高級品です。
- 茶の湯で使用する池田炭もクヌギです。
千利休は炭が爆ぜるのを嫌い、
白炭のようにもう一度燃焼させて炭化度を高めたクヌギ炭を使用したそうで、
これを利休の二度焼きの炭というそうです。
- 輸入品ではマングローブやユーカリなどが多く使用されているようです。
ヤシガラ活性炭も黒炭の一種です。
-
- 白炭:ウバメガシ(馬目樫)--- 紀州備長炭(和歌山) 土佐備長炭(四国)
- 中国製の備長炭も樹種としてはウバメガシです。
- アラカシ --- 日向備長炭(九州) 紀州備長炭(和歌山)など
※紀州備長炭はウバメガシとアラカシの
2種類があります。
- ナラ --- 秋田など東北の白炭
-
- 黒炭は火が着きやすく、扱いやすい炭です。
価格もリーズナブルですが、粗悪品が多いので、
できれば国産のよい炭を大切に使ってください。
- 備長炭などの白炭は火が着きにくく、扱いにくい炭ですが、
炭化純度が高く硫黄分など不純物が少ないので
燃焼時に臭いをほとんど出しませんし、
国産のものはパチパチ爆ぜませんので室内での使用に向いています。
高価ですがその分燃焼時間が長いので、
途中消火するなどして大切に使ってください。
|
よい炭とはどんな炭?
- 木炭の良し悪しは使用目的によって異なります。
- 一般的には、着火しやすく、煙りが出ず、異臭がなく、炎が上がりにくく、
火力が安定していて長時間燃焼し、立ち消えしない、安い、
といったところでしょうか。
実際には長時間燃焼する炭は着火しにくく高価ですから、
なかなか思うようにはいきません。
- 工業用など用途によっては立ち消えしたほうが経済的とか、
煙も臭いもおかまいなしとかいうこともあるようです。
焼き肉店では燃焼時間が長い炭は高価な上に調理が終わっても燃焼していて
無駄が多いとか、用途によって良し悪しが決まるとしかいえません。
木炭の特徴を知って相応しいものを選ぶ。
あとはふところ具合との相談といったところでしょうか。
私個人としては、上質の木炭を大切に使うのが一番お得だと思います。
- それと以外と大切なのは木炭の大きさです。
小粒のものや細いものは火付きがよく、表面積が広いため火力があります。
そのかわり燃焼時間が短くなります。大粒のものや太い炭はこの逆です。
備長炭を使用している焼き鳥屋さんでは、火力のある細い炭が好まれます。
じっくり焼く鰻屋さんでは逆に太い炭が好まれます。
家庭用の七輪では小粒でないと入りにくいとか、
火鉢で使用するなら大きくないと火持ちがわるいとか
炭の大きさや形にも特性があります。
特に備長炭は自分でカットできません(正確には大変困難)から注意が必要です。
|
|
七輪本舗TOPへ
|