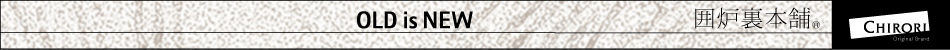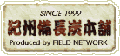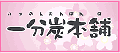| 骨酒器 |
骨酒器は、囲炉裏でじっくり焼いた川魚に熱燗をそそぎ、徳利として使うものです。
魚が入りやすいように横長になっています。
※火にかけて酒を温めるものではありません。
|
| KZ-32 骨酒器(杯2個付き) 2,200円(税込・送料別) |
| |
 |
全長:32cm
高さ:18cmほど(取っ手まで含む)
最大容量:700ccほど(使用適量は半分の2合ほど)
杯2個付
日本製(美濃焼:岐阜県)
★ごめんなさい!★
ただ今在庫切れです。
入荷予定は未定です。
 |
 |
 |
 |
 |
| ※パソコン画面と実物は色合いが異なるかもしれません。ご了承ください。 |
箱入りでお届けいたします。 |
 |
囲炉裏端に似合う骨酒器です。
2合(360cc)ほどが適量です。
最大容量は700ccほどありますが、傾むくと口からこぼれるので控え目にしてください。 |
|
★ 骨酒の作り方 ★ |
|
○2つの方法
骨酒は囲炉裏でじっくり焼いた魚をそのまま入れる方法と、
身を食べた後の頭や骨を焼いたもの入れる方法の2つがあります。
本来的には食べ残った骨の有効利用?ではないかと思いますが、
現在は身のついた魚を使うことが主流のようです。
できれば両方をお楽しみください。
■魚 種
イワナ、ヤマメ(アマゴ)、アユなどの川魚を使うのが一般的ですが、海魚も美味なものが多数あります。
川魚で最もポピュラーな魚はイワナで、旅館や飲食店の多くで使われます。
ヤマメ(アマゴ)はイワナに近い味です。アユはまた違った美味しさがあります。
海魚はタイ系を中心にお頭を使った骨酒がありますが、何れも美味です。
※海魚の場合はこの形状の骨酒器でなく、お椀形状の骨酒器を使います。
■魚の調理
○ポイントは
1 )魚臭さを残さない 2 )コゲ味を出さない 3 )魚の旨味を引き出す の3つです。
○下処理
エラ、ハラワタ、血合いを丁寧に取り除き、よく水洗いします。
焼き終わってから取ってもかまいませんが、骨酒用として焼くなら、できれば事前に取ってください。
○塩
塩はしなくてもかまいませんが、魚に塩をすると、水分と共に臭みを抜くことができます。
ただ、塩はお酒の味に影響しますので、好みにより微妙なところだと思います。
塩はしないか、薄塩かどちらかでお試しください。
塩は薄塩にして、骨酒にする前に払い落としてもかまいません。
|

アユ |
|
|
○焼き方
囲炉裏でじっくりと時間をかけて遠火で焼きます。
炭火の上は上昇熱(対流熱)が多いので、なるべく横方向に飛んでくる赤外線(輻射熱)で焼くのが理想的です。
塩焼きの魚のように強火であっさり焼くのではなく、できるだけ長時間かけてじっくり焼きます。
長時間焼くと魚の水分がなくなり、旨味が変化し、凝縮されます。
魚臭さが残るより、よく焼けた方がよいと思いますが、コゲ風味がでるほど焼いてしまわないことも大切です。
|
| |
 |
囲炉裏で炭火から横方向に飛んでくる赤外線で
じっくり焼くのが理想的です。
最低1〜2時間、時には5時間、10時間と焼かれます。
←イワナ |
| |
 |
こがさないようにじっくり焼かれた魚は、
水分がなくなり特有の旨味が増します。
←アユは何にしても美味です。
塩を払い落として骨酒器に入れます。 |
 |
昔は囲炉裏の上に吊るされた「弁慶」に焼いた魚を刺し、
数日間干したものを骨酒にしたり、そばの出汁に用いました。
海の幸が入手できない山間部ならではの知恵です。
←囲炉裏で沢山のイワナが焼かれています。
(高遠そばで有名な大内宿・三澤屋さんの囲炉裏) |
○お酒
一般的にお酒はあまり上等でなくてよい・・・とされています。
魚味が付く上にとびきりの熱燗にするので、もったいない!ということだと思います。
60度〜70度くらいとかなり高温にしたものを注ぎます。
できればお酒も風情をもって、
囲炉裏の徳利や酒燗器で温めてはいかがでしょう。
|
 |
 |
 |
|
| 囲炉裏の徳利 |
炭火にかける酒燗器 |
炭火酒燗器 |
|
 |
温度は60度〜70度程度が一般的。
熱くしすぎないようにご注意を!
(写真は「おかんメーター」でお酒の温度を計っているところです。) |
○召し上がり方
骨酒器に魚を入れて、燗したお酒をそそぎ、少し身をほぐして旨味を出します。
2、3分待ってから♪♪♪ |
 |
骨酒器は事前に弱火の炭火で温めておきます。
直火は不可ですから、触れる程度の温度にしてください。
※高温になると割れてしまいます。 |
 |
スルメでも肴にしてちびちびいかが? |
ご注意!
骨酒器は高温にさらされると割れてしまいますので、直火使用はできません。
炭火、ガス火共に不可です。お酒の温めは別の容器をご使用ください。
※少量の炭火で保温する程度なら大丈夫です。 |