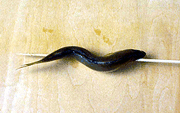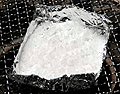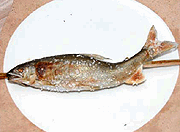|
「これ食べた〜い」は、なによりも炭火好きで食いしん坊の私が、
どうせなら写真でも撮って皆さんに紹介しよう、
皆さんから情報を集めよう、ということでスタートしました。
これから七輪料理を始めようという初心者の方々でもわかりやすい
七輪料理講座としてやっていこうと思います。
といっても私自身勉強しながらのご紹介ですから大したことはない・・・です。
気分次第のスローペースですが、
延々に続ける特集として炭火料理をご紹介していきます。
ちょっとだけ「通」になってください。
そして七輪料理を楽しんでいる皆様、是非メールください。
どんな情報でも大歓迎です。
|
|

|

|
これは和歌山県日高川の天然鮎。
|
|
|
ちょっと鮎通になるお話し
|
|
鮎の生態基礎知識
|
|
鮎は秋9〜12月ごろ(地域により異なる)に川で産卵。
ふ化した仔魚は海へ下り、春まで海でプランクトンを食べて成長します。
3〜5月に川へ遡上し、徐々に石についたコケを食べるようになり
(鮎が食べた跡を「はみあと」という)、秋の産卵期まで川で暮らし、
産卵後に「落ち鮎」となり一生を終えます。
年魚といい通常1年で生涯を終えますが中には2年魚もいるそうです。- 海へ下る「海産」、湖(琵琶湖)へ下る「湖産」、
「人工産(養殖)」の3種がいます。
- また、琵琶湖には産卵直前まで川を遡上せず
体長10cm程度にしかならない「コアユ」がいます。
- 海や湖で幼魚期を過ごすわけですから、
ダムより上流の鮎は全て放流ものということになります。
- 香魚と呼ばれるのは、生でも魚臭くなく、スイカのような独特な臭いがするためです。
この臭いは生息する川によって違い、その川のコケの香りと言われています。
そして食べましても生息河川により明らかに味が違うそうです。
ですから鮎通の人は捕れた川にこだわらなければならないそうです。
|
|


いずれも上が養殖 下が天然
|
まず決定的に違うのは、尾ビレ、背ビレなどのヒレ。
天然ものは大きくてシャープに尖っています。
養殖ものはよく肥えており体格が立派ですが、
ヒレは小さいのが特徴です。
養殖魚はヒレを育てる遺伝子が薄い?のでしょうか。
天然ものは胸ビレ上部にある半月状の
黄色い模様(追い星)が鮮明です。
この追い星のはっきりしたものが
縄張り意識が強いといわれています。
養殖ものの模様が薄いのはそのせいでしょうか?
体色は養殖ものの方が濃い緑色ですが、
これは天然も養殖も生育環境により
色が異なるのかもしれません。
でも、養殖ものでも十分おいしいです。
|
|
お料理
|
|
串にさして塩をふり、焼くだけ。
やっぱり串焼きがなんとも魅力的です。
ただし、本来の串焼きは魚の水分をとばしてじっくり焼きあげるもの。
1時間以上は必要です。
間違ってもハラワタを取り除いてはなりませんゾ。
|
|
|
1. 洗う
まず、粗塩でもみ洗いし、ぬめりをとります。
塩は一旦洗い流します。
(ここまでの行程は不要との意見もありますが・・・)
|
|
|
2. 糞を抜く
鮎のお腹を強く押して
肛門から絞り出すように糞をぬきます。
うまく抜けなくても気にするほどのことではなさそうです。
|
|

尻尾を上に跳ね上げて、
背ビレをピンと立てるのが
踊り串の秘訣のようです。
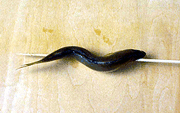
|
3. 踊り串を打つ
けっこう簡単ですので、是非チャレンジしてください。
(注)串をぬうように刺そうとすると難しいです。
ポイントは、先に鮎を踊った形にしてから、
単に真っ直ぐに串をさせばいい。
そういうイメージでやれば簡単。
上半身と下半身?の2回にわけて、
左手で鮎をくねらせて指で固定し、
右手で串を回しながらゆっくり刺してください。
鮎は皮も骨も柔らかいのでゆっくりやれば簡単に刺せます。
口から刺してもよいのですが、
細い串なら目から刺す方が踊らせやすいです。
|
|

|
4. 塩をする
胴体には軽く振りかける程度。
ヒレにはこげにくいようたっぷりと化粧塩をします。
全部のヒレにすりこむように塗ってください。
|
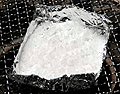
|
粗塩をアルミホイルで焼き塩にすると、
サラサラした使いやすい塩になります。
|
|
|

本来は2時間くらいじっくりと。
|
5. 焼く
普通に鮎を水平にしてさっと焼き上げたもの、
串を立てて遠火でじっくり焼き上げたもの、
最初は両方を味わってください。
さっと焼く場合は、皮が身から離れて膨らんできて、
その皮にこげ目がついたら裏返して
反対側を同じように焼きます。
焼きすぎは禁物です。
※網焼きと同じ焼き方です。
串を立てたじっくり焼きの場合は、好みによりますので
いろんな焼き時間を楽しめばよいと思いますが、
本格的な串焼きを味わうには、
最低2時間は必要です。
天地を逆さにしたり、回したり、じっくりと
丁寧にしないと一部だけ焦げてしまうのでご注意を。
|
|

|
串を立ててじっくり焼きをすると
美しく焼けます。
|
|

|
【おすすめの焼き方】
串を立てて焼きながら、
1匹〜2匹ずつ平焼きで焦げ目をつけていきます。
これだと1時間もあれば串立て焼き独特の味も楽しめます。
身がしまって、串のまま食べられます。
|
|
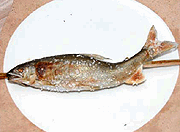
|
6. 食べる
そのままで十分美味しいのですが、
一般的には、「たで(蓼)食う虫も好きずき」の「たで」を
すりつぶしたものに酢を加えた、たで酢で食べるようです。
市販品もあります。
串を立ててじっくり焼きしたものは
脂分が少なくなっていますが、
身が引き締まって歯ごたえがあり、
酒の肴に向いています。
串のまま食べましょう。
|
|
天然、養殖といっても一概にはいえないとは思いますが、
この日の鮎に限ってお話ししますと・・・
|
-
- ○天然もの
- まず身の色はややグレーがかった色で脂肪のせいか透明感があります。
- 食べるとまさに川の味(コケの味)というのでしょうか鮎独特の味がします。
まさにこれが天然鮎の味。この味が川によって変わるんだと思います。
悪く言えば川臭い!この独特な味わいを嫌う方は養殖ものがおすすめです。
全身にくまなく脂がのっています。
-
- ○養殖もの
- 身の色は、鯛の身のように白く、明らかに天然ものとは違います。
焼いている時は天然ものよりたくさんの油がしたたり落ちたのに、
ぱさっとした感じで脂肪がありません。
どうやら脂肪と淡泊な白身が完全に分離しているようです。
味は天然ものに比べると海の魚のような感じで、さっぱりしています。
さっと焼き上げた方が脂が残って美味しいと思います。
川の味はありませんが美味しいです。
養殖でもやっぱり鮎!
好みによっては養殖の方が美味しいといわれる方も多いと思います。
- 天然ものが美味いに決まっている!と思いこむのはどうか・・・。
|
|
ブラックバスは鮎とともに
- 全国の河川には琵琶湖から大量の稚鮎が放流されます。
この稚鮎にブラックバスやブルーギルの稚魚が混ざってしまい、
全国の河川に広がったそうです。
エサ付きで放流されるブラックバスは幸せ者?です。
DNA鑑定すれば琵琶湖産かどうかわかるんでしょうね。
天然鮎の価格
- 和歌山県日高川近辺の天然鮎の価格は、
元気に泳ぎ回るものなら、一匹250円が相場だそうです。
これは釣り人が業者さんに引き渡す時の価格です。
地元の人はよく業者さんに頼まれて、趣味を兼ねて友釣りをするそうです。
ウラヤマシイ・・・。
ここの鮎なら死んでいても250円という地域限定ものもあるそうです。
料亭での末端価格はいくらなんでしょうか?ね〜。
|
|
vol.1 秋刀魚 を見る
vol.2 烏賊の干物 を見る
vol.3 蛤 を見る 七輪本舗TOPへ
|